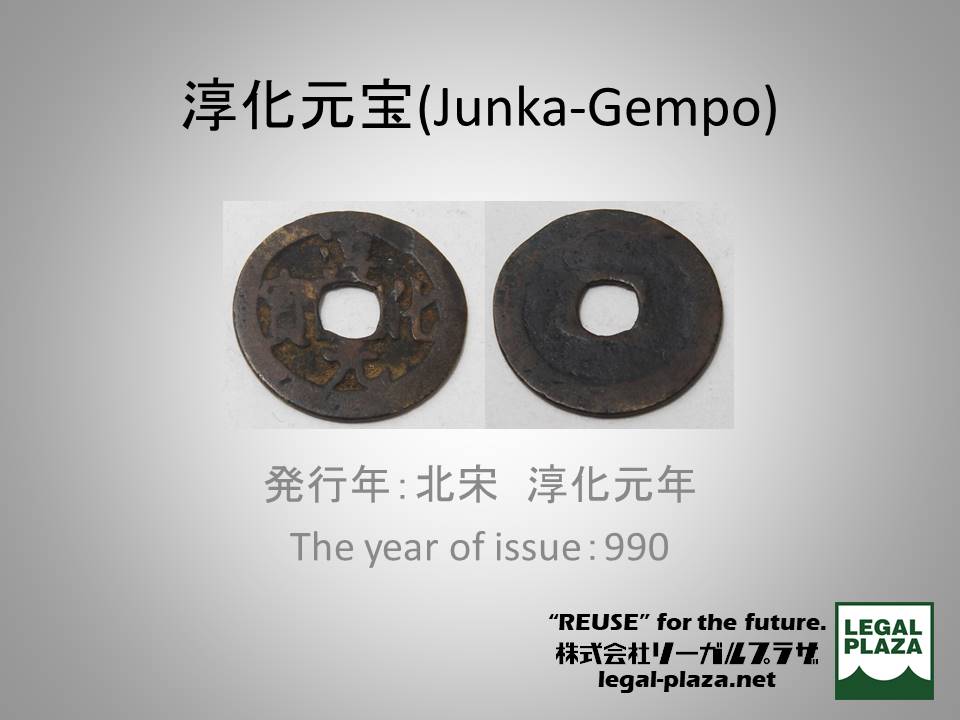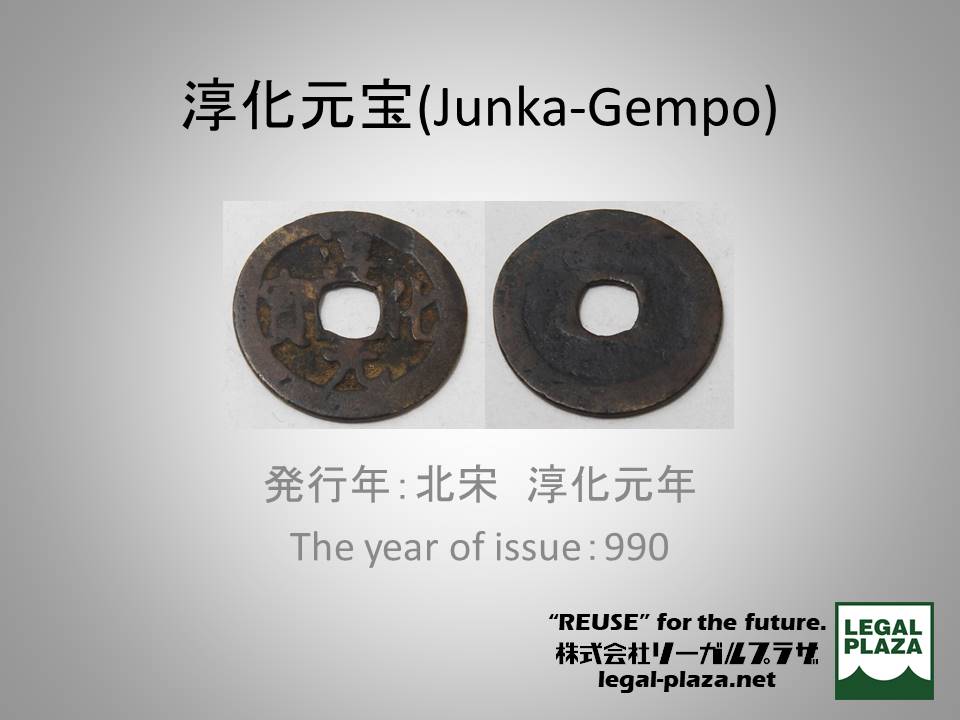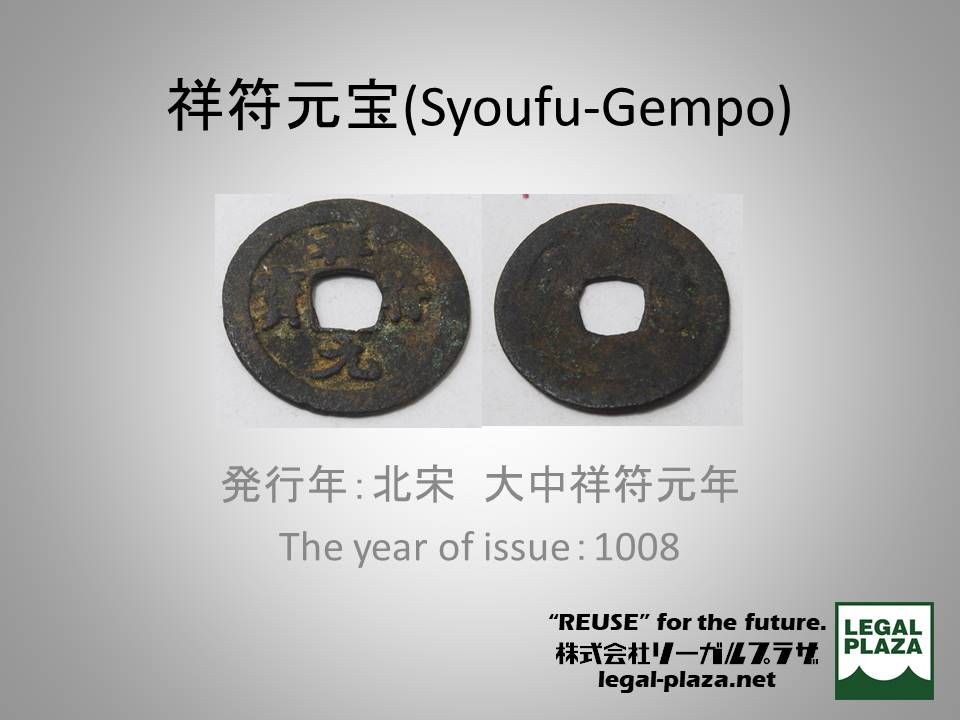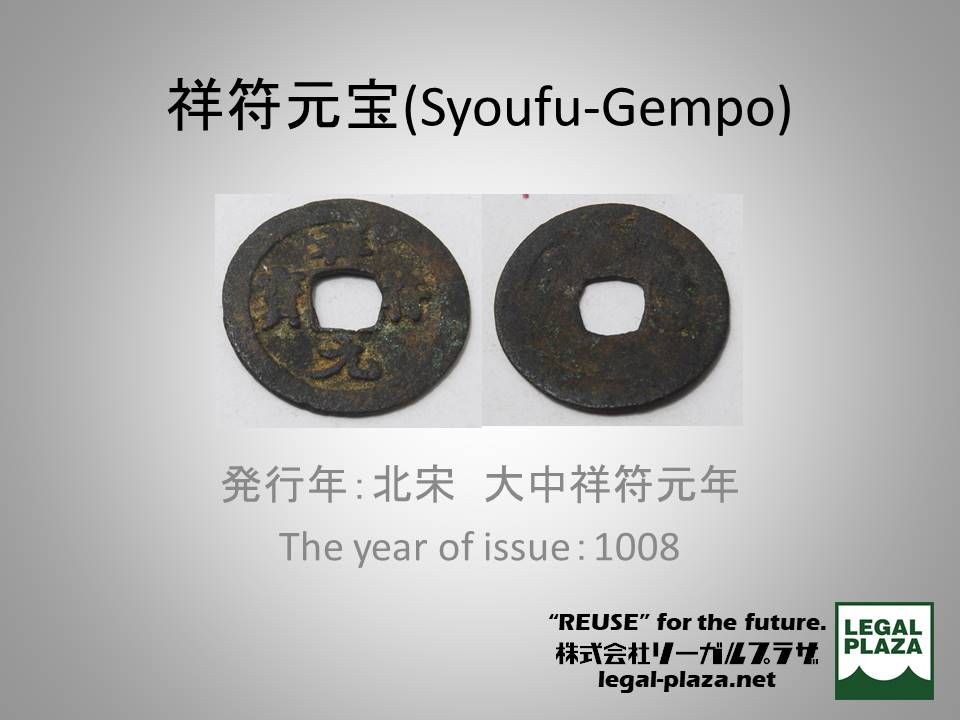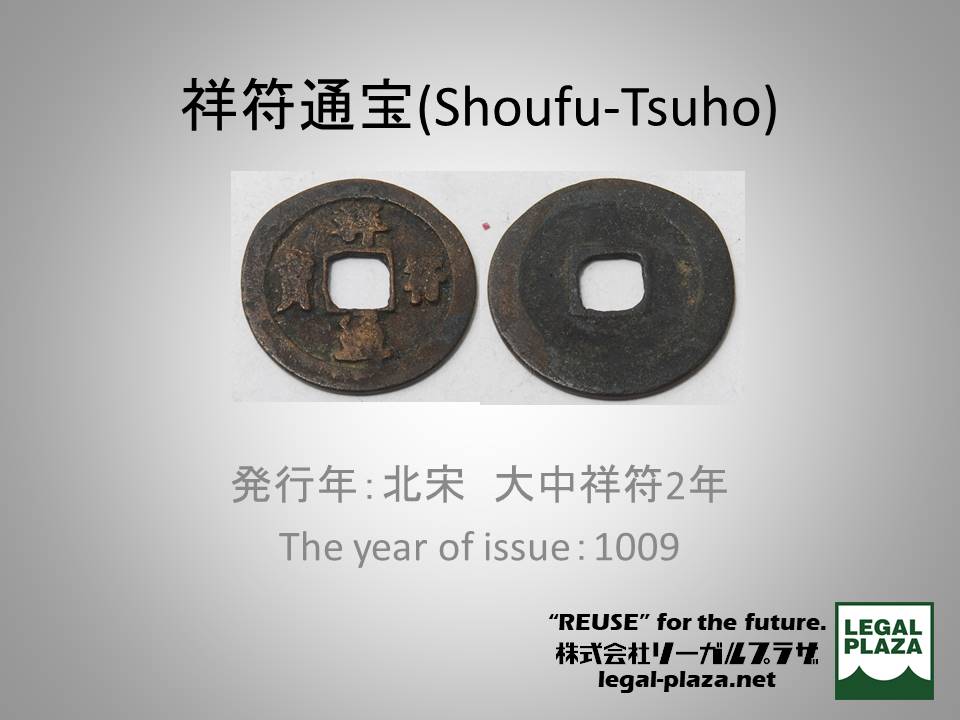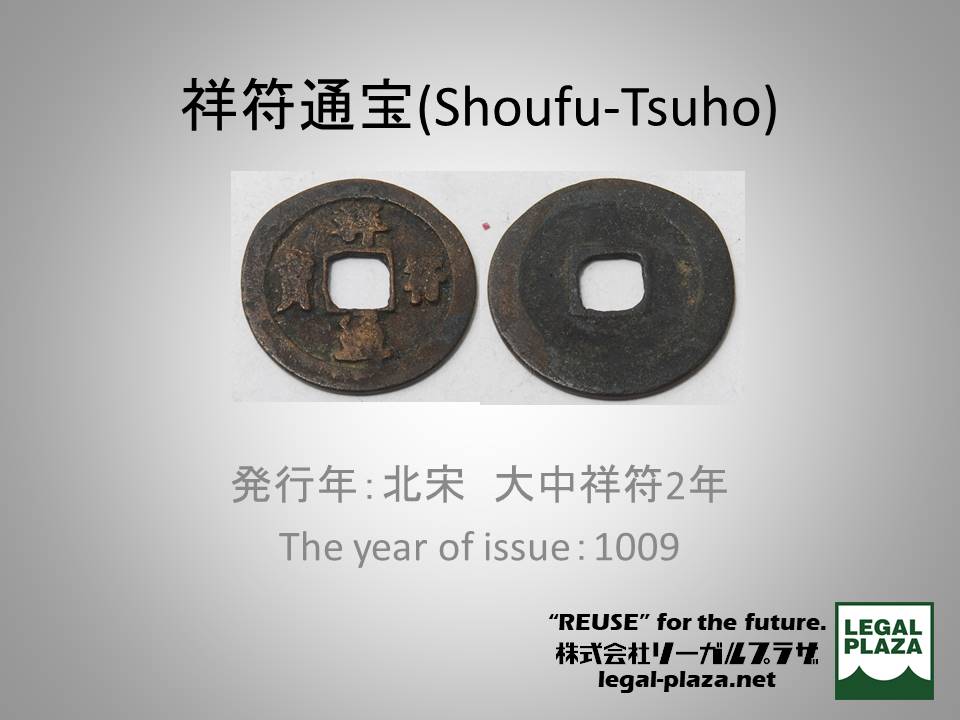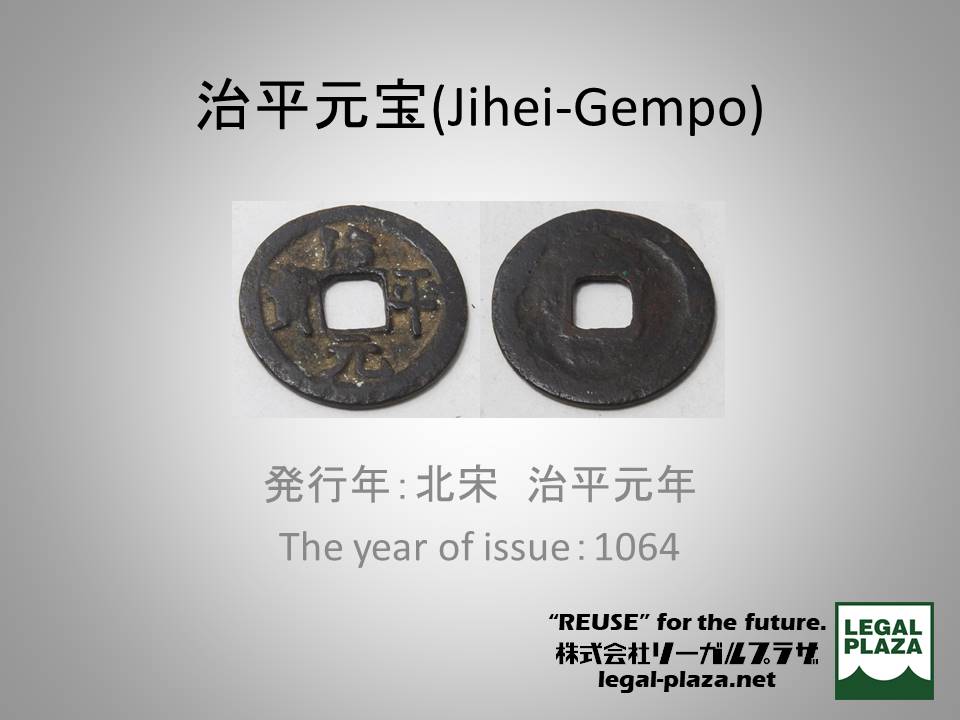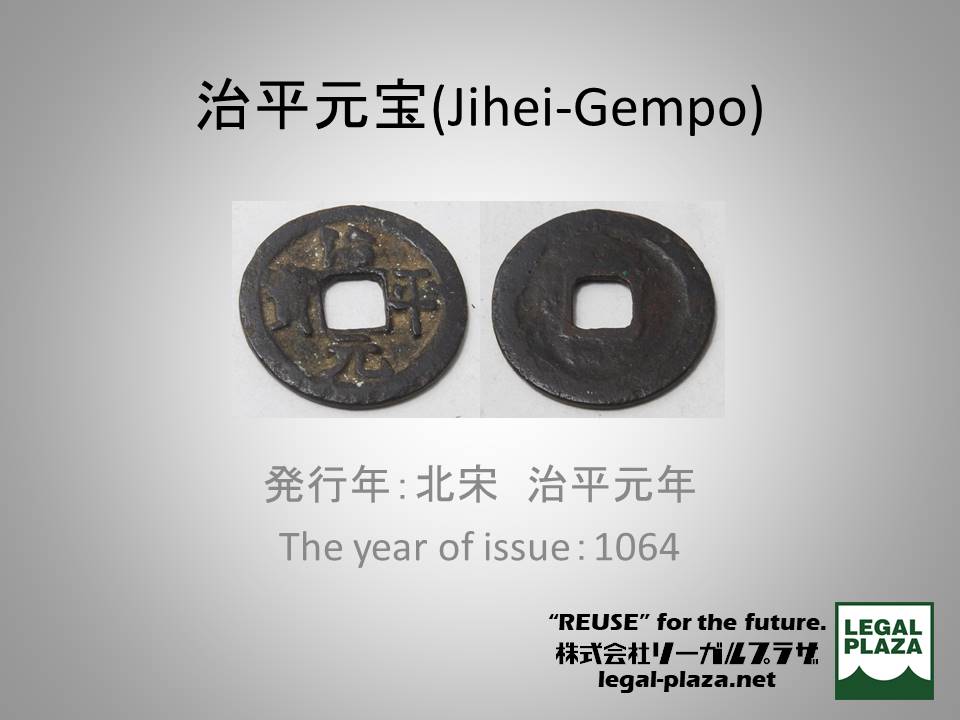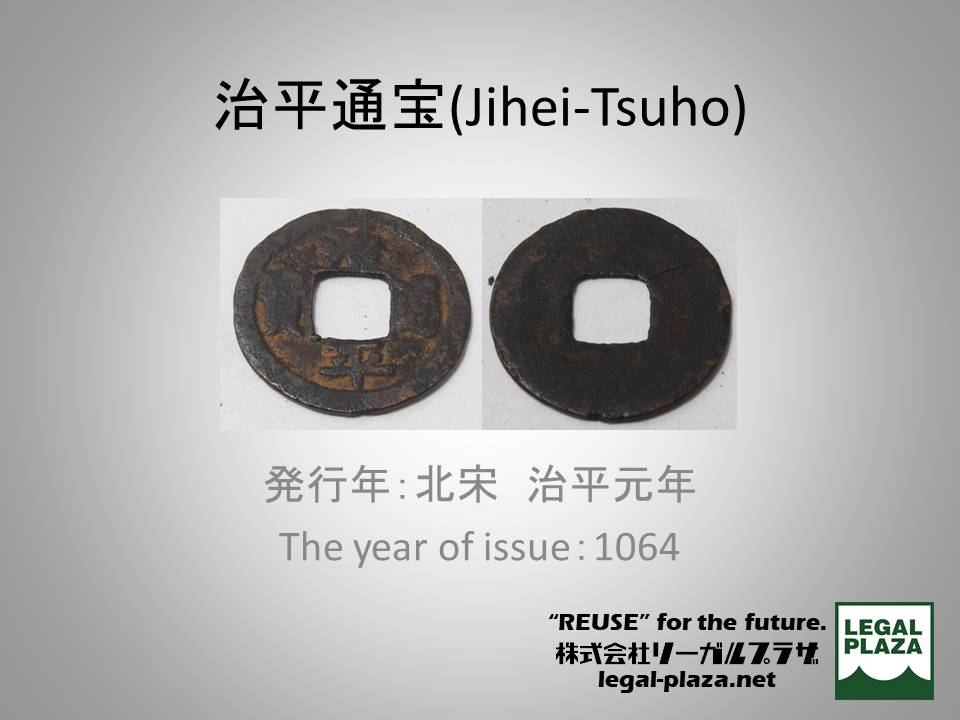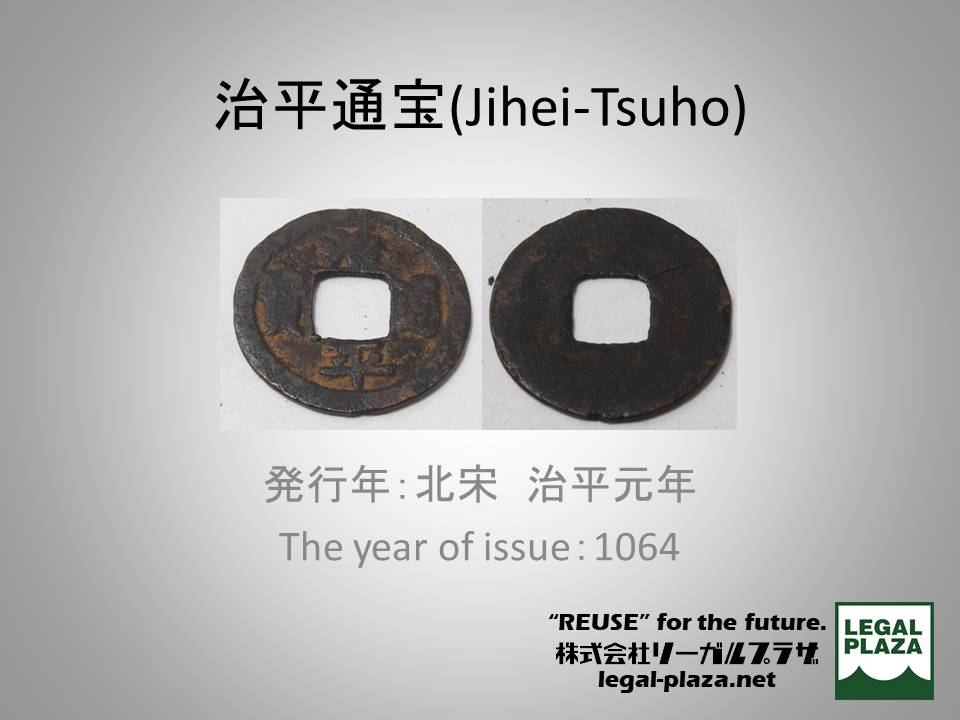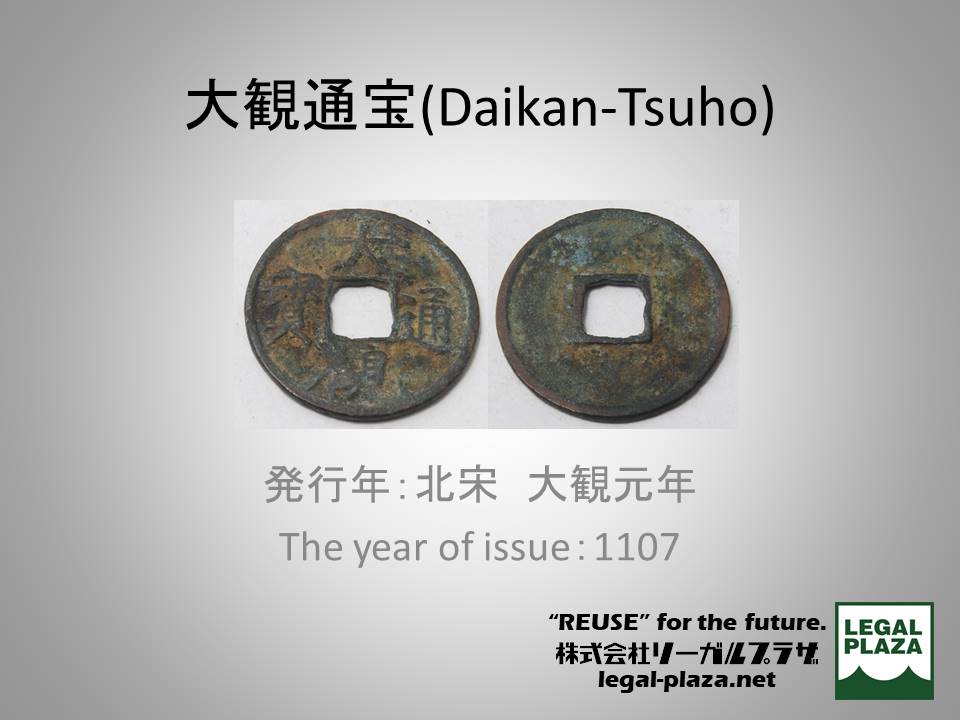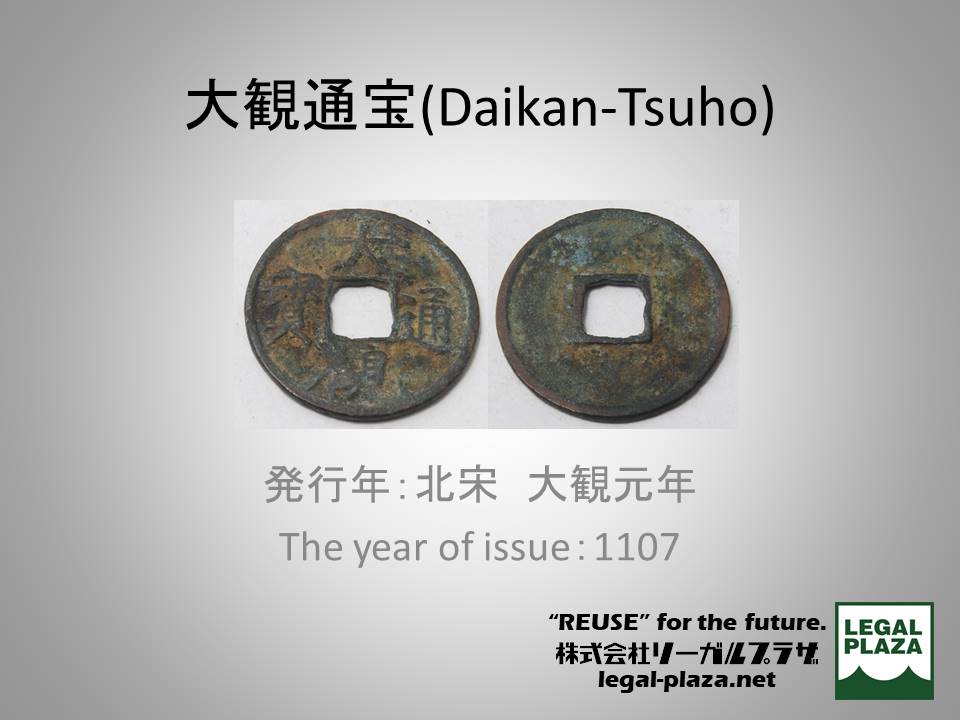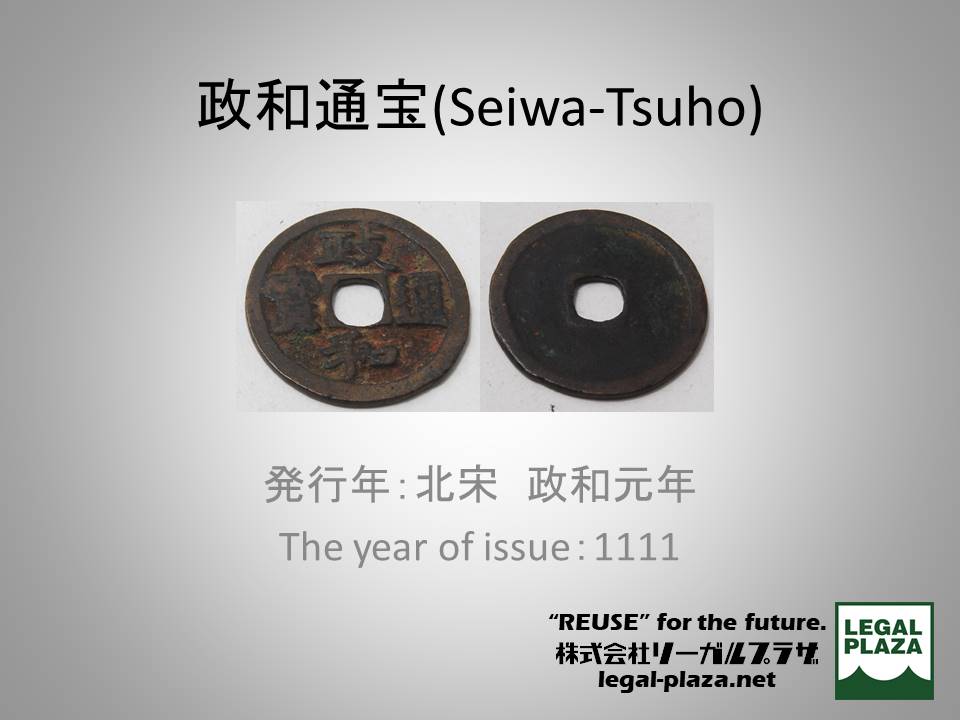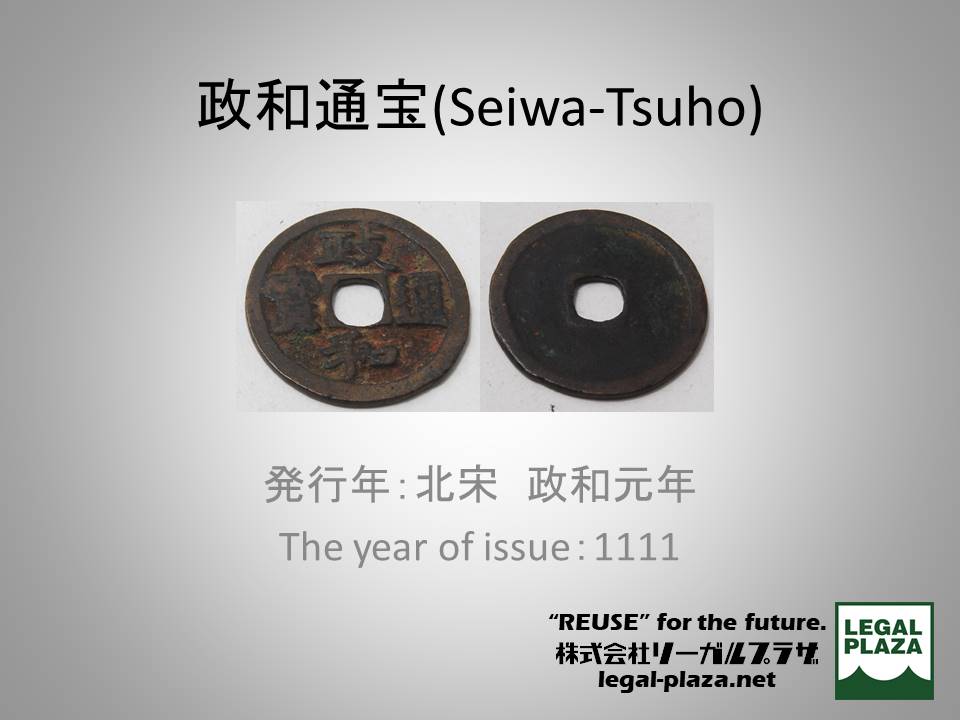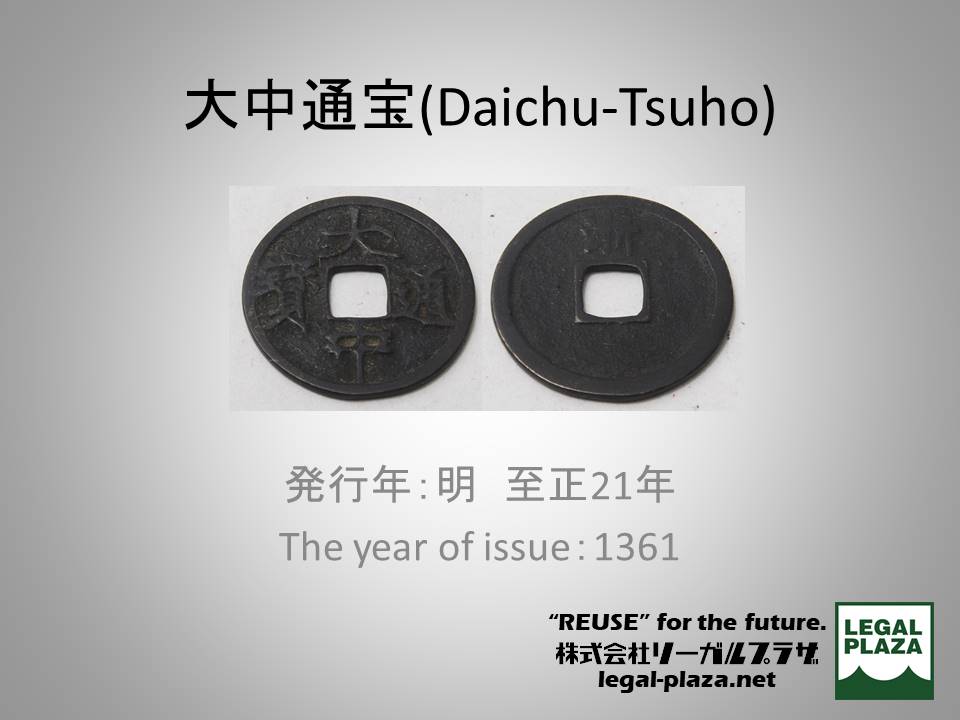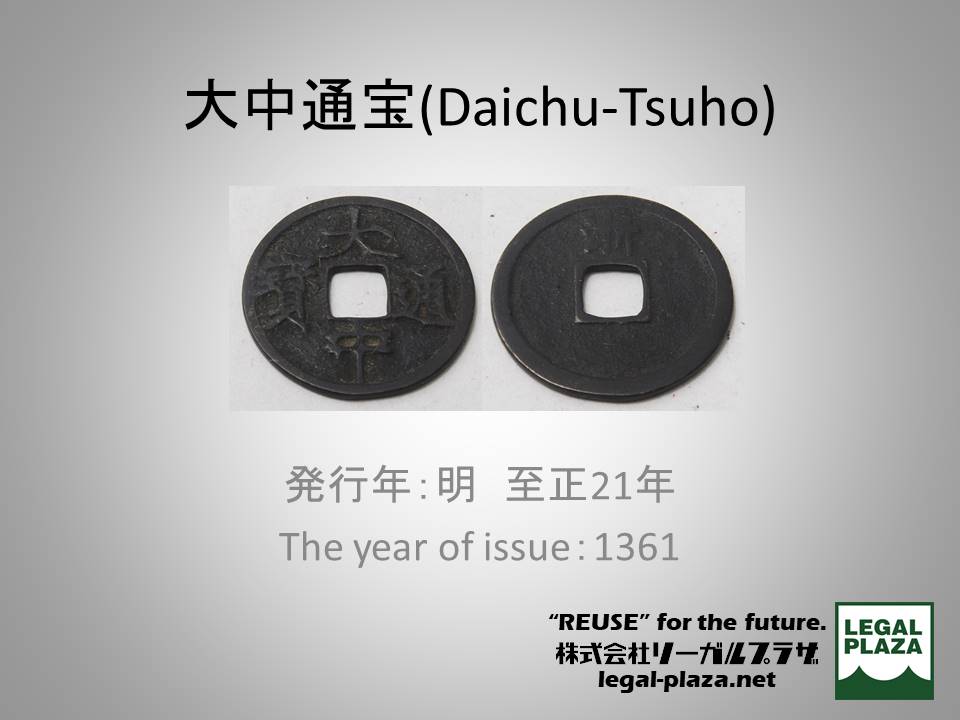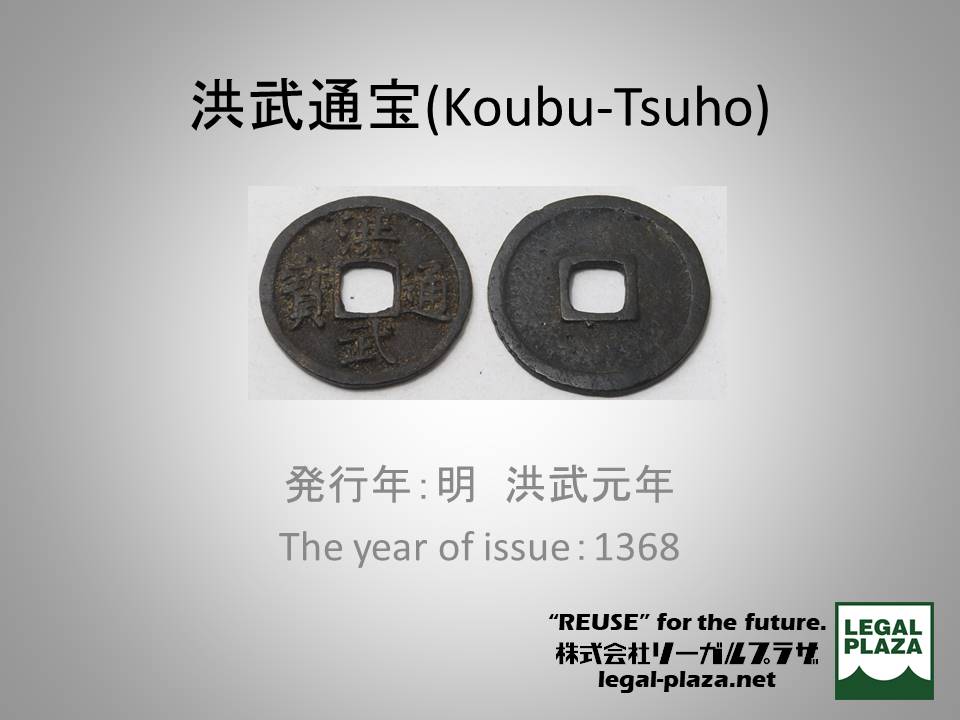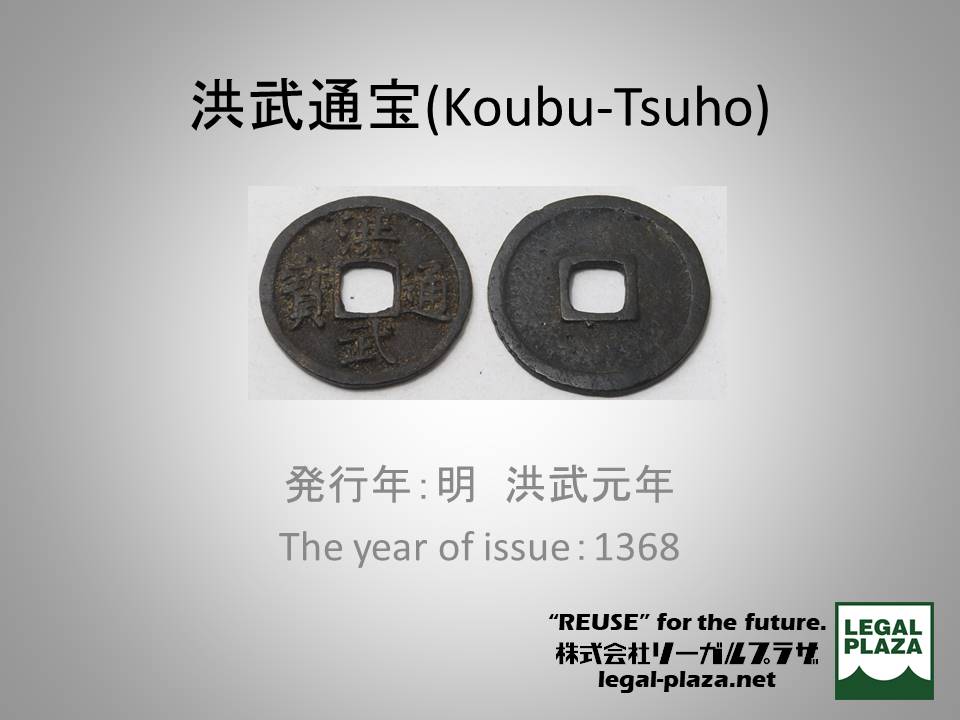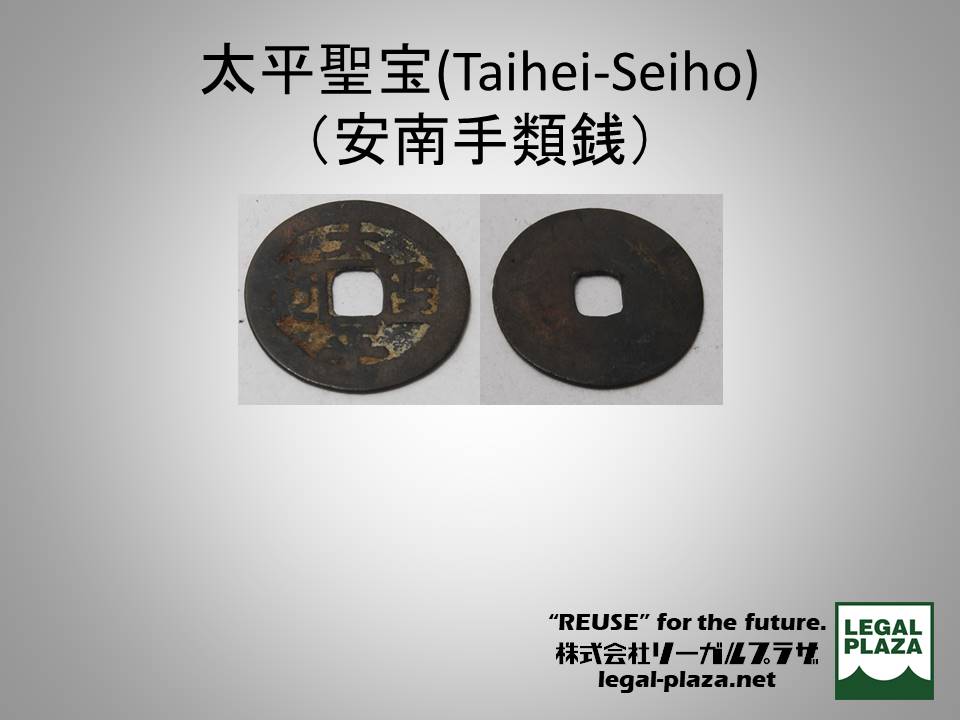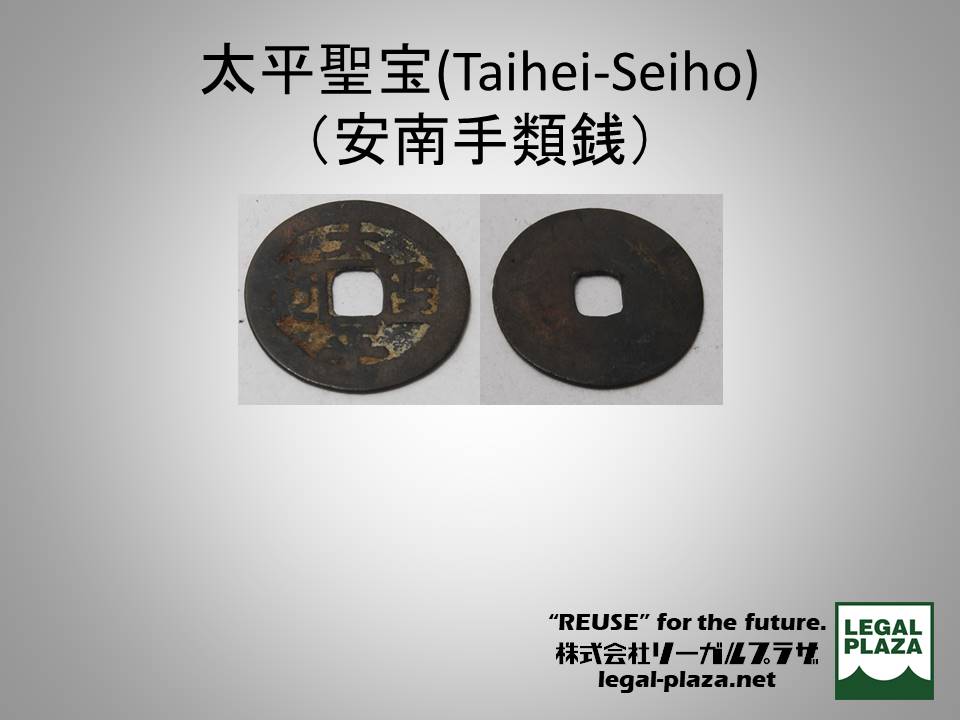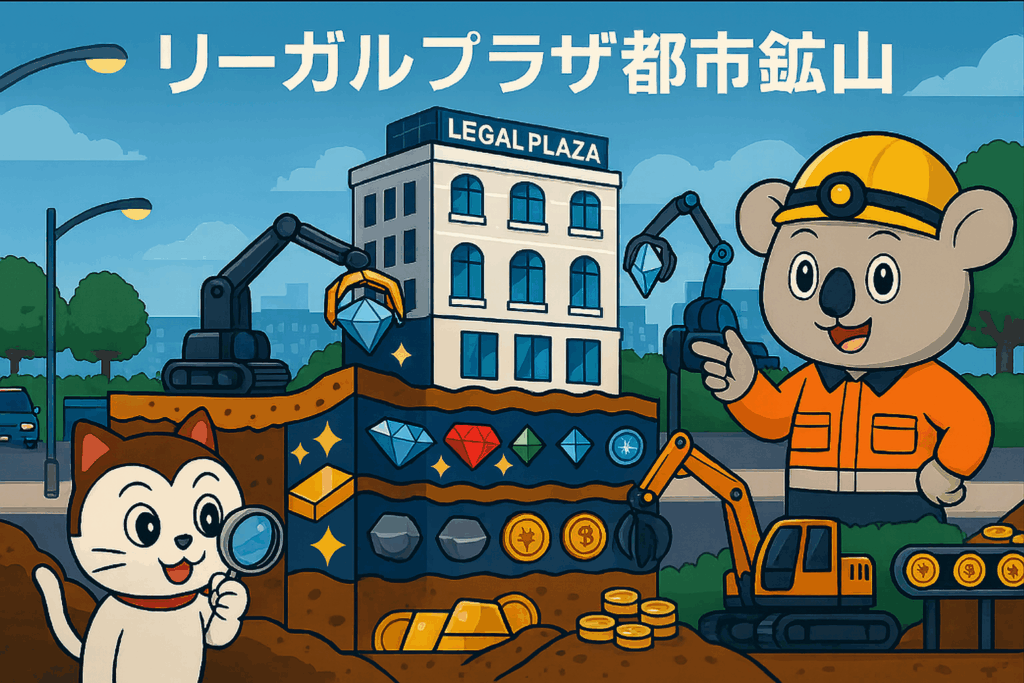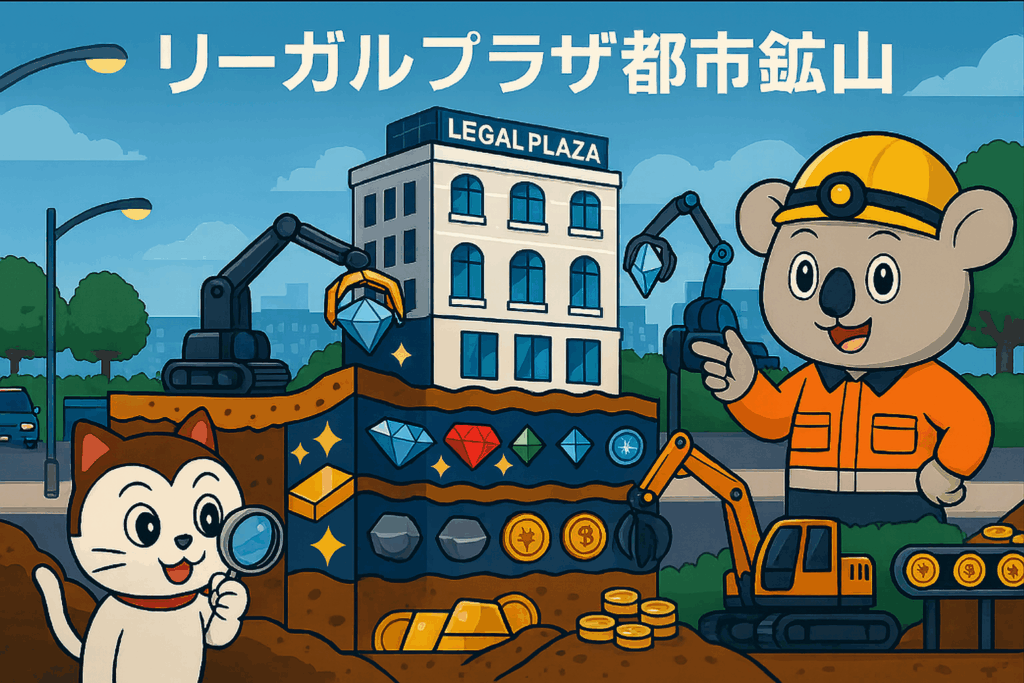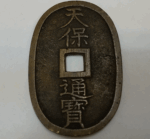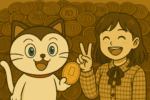🟨第1章:たまもも探検隊、古銭のルーツを探る!
 もも(好奇心旺盛なJD)
もも(好奇心旺盛なJD)ねぇたまちゃん、日本のお金って、最初から日本で作ってたの?



実はね、日本最初の流通貨幣は“外国製”だったんだよ〜



えっ!?外国のお金!?どうして!?



そう、それが“渡来銭(とらいせん)”!つまり中国や朝鮮半島から海を越えてやってきたお金さ!



うわぁ〜、海を渡ってやってきたお金って、なんかロマンある〜〜〜!
🟨第2章:そもそも渡来銭ってなに?
渡来銭とは、中国や朝鮮などから日本に輸入・流入し、実際に日本国内で使用された外国貨幣のことです。主に「銭貨(せんか)」、つまり金属でできた丸い穴あき硬貨が中心でした。
| 分類 | 地域 | 代表的な銭種 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 唐銭 | 唐(中国) | 開元通宝 | 最古の流入 |
| 宋銭 | 宋(中国) | 咸平元宝、祥符元宝など | 日本で最も流通した |
| 明銭 | 明(中国) | 永楽通宝など | 室町末期~江戸初期に人気 |
| 高麗銭 | 朝鮮半島 | 高麗通宝など | 数は少ない |
| その他 | 元・清・ベトナムなど | 稀に確認される程度 |
🟨第3章:最古の渡来銭「開元通宝」との出会い







“開元通宝”ってなんだか開運しそうな名前〜!



ふっ、唐の時代、紀元621年に鋳造された世界的にも有名な貨幣なんだ。



えっ!?そんな昔のお金、日本にあったの!?



奈良時代にはすでに輸入されていた形跡があるよ。つまり、日本の貨幣文化は中国の影響からスタートしてるんだ。
🟨第4章:日本を席巻!宋銭ブーム








実際に日本の市場で最も流通したのは**宋銭(そうせん)**です。宋の時代(960〜1279年)に鋳造された膨大な数の貨幣が、日本に正規・密輸を問わず入り込みました。
- 代表例:
- 咸平元宝(かんぺいげんぽう)
- 祥符元宝(しょうふげんぽう)
- 元豊通宝(げんぽうつうほう)
- 大観通宝(たいかんつうほう)



種類めちゃくちゃ多くない!?全部集めたらコレクター界のヒーローじゃん!



当時は“質より量”!日本で足りない小銭をまかなうために、宋銭は重宝されたんだ。
🟨第5章:なぜ日本では貨幣を自前で作らなかった?
日本は奈良時代に和同開珎などを鋳造したものの、平安時代になると貨幣鋳造が止まり、物々交換や米経済に逆戻りします。



技術の継承も難しかったし、需要に対して安定した供給もできなかったんだ。



そっか〜、お金作るのって、簡単そうに見えてめちゃ大変なんだね。



そう、それで“輸入しちゃえ”って流れに。
🟨第6章:明銭のスター「永楽通宝」登場!




永楽通宝(えいらくつうほう)は、明の永楽帝時代(15世紀)に登場した銭貨。
この永楽通宝は、江戸時代に入っても使われ続けた異例の長寿硬貨なんです!
- 材質:銅
- 重量:約4.2g
- 特徴:書体が美しく、日本でも鋳造された(模鋳銭)



え、つまり日本製の“ニセ永楽”もあるってこと!?



うん、“私鋳銭(しちゅうせん)”って言って、民間や藩が勝手に作ったりもしてたの。
🟨第7章:渡来銭は流通だけじゃない!デザインの師匠だった?
渡来銭は日本の貨幣デザインにも強い影響を与えました。
- 文字の書体
- 穴あき形状
- サイズの規格
- 通宝という名称の採用



つまり、今の硬貨の“穴”も、中国銭のマネだったんだね!



うん。寛永通宝なんかは“永楽通宝”の影響をモロに受けてるんだ。
🟨第8章:江戸幕府と渡来銭の断捨離!




江戸幕府は、国内の貨幣制度を統一すべく、渡来銭の使用を段階的に禁止していきます。
- 正徳4年(1714年):「渡来銭の使用禁止」
- 以後、寛永通宝などの国産銭に一本化



でも、禁止されるくらい流行ってたんだね〜



市場では“信用されてた”ってことでもあるよね。時代が変わっても通用したってのはすごいこと。
🟨第9章:実は今でも手に入る!?渡来銭の収集事情
現代では、渡来銭は以下の場所で手に入ることがあります。
- 古銭市場・骨董市
- ネットオークション(ヤフオク、メルカリ等)
- 古美術店
- 展示会・博物館
| 銭種 | レア度 | 相場(目安) |
|---|---|---|
| 開元通宝 | ★★★★☆ | 数千円〜1万円以上 |
| 咸平元宝 | ★★★☆☆ | 500円〜5,000円程度 |
| 永楽通宝 | ★☆☆☆☆ | 100円〜2,000円(状態による) |



やったー!コレクション始めちゃおっかな〜!



ただし、模造品も多いから注意が必要だよ!とくに“和製永楽”は見分けが難しい…
🟨第10章:渡来銭が教えてくれるもの
渡来銭の存在は、以下のような歴史的価値があります。
- 日本の貨幣文化は“輸入”から始まった
- 中国との交易・文化交流の証
- 経済的不足を他国の制度で補った柔軟性
- やがて独自文化を育てた進化の起点



最初はマネでも、そこからオリジナルを生み出すって、なんか感動だよね…!



ほんとに。“真似る”って、“学ぶ”ってことでもあるんだ。
🟨たまちゃんまとめ:渡来銭は日本の“お金のDNA”だった!



今の円や硬貨があるのも、唐・宋・明からの“学び”があったからこそ。
たった1枚の古銭から、国と国のつながりや、時代の流れが見えてくる。
それが古銭のロマンです。
~渡来銭ミニカタログ~