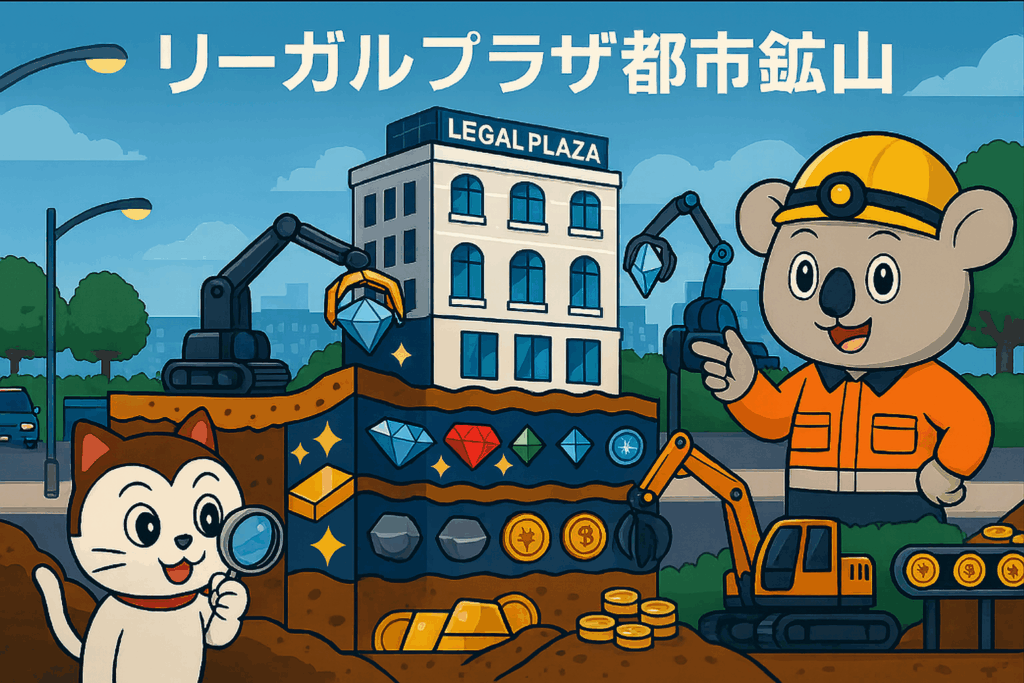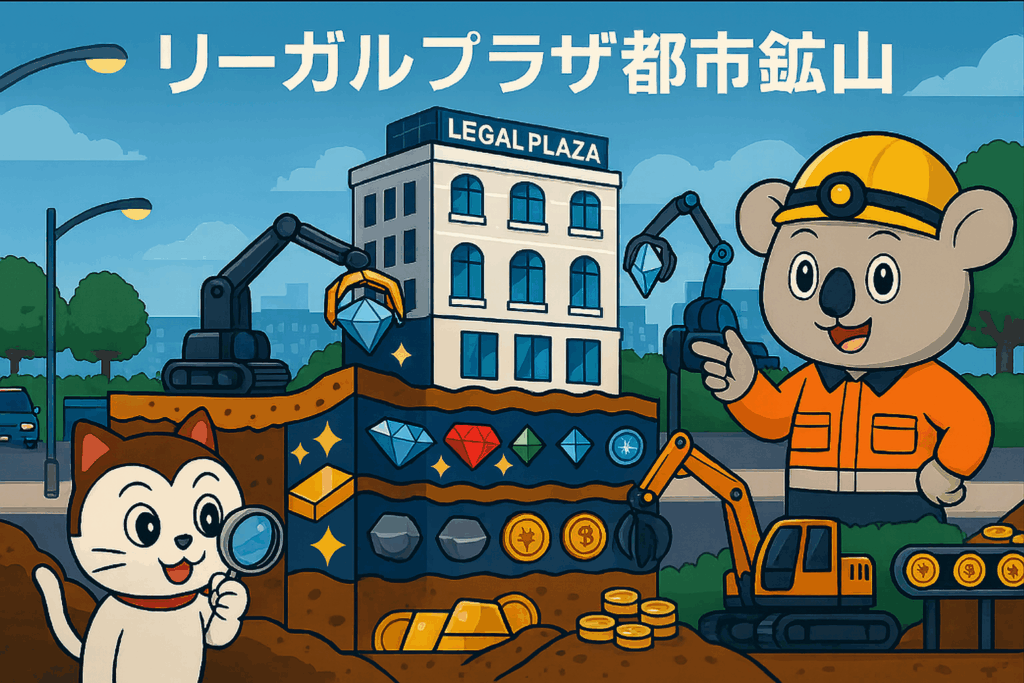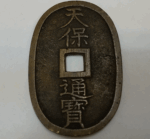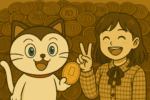もも(好奇心旺盛なJD)
もも(好奇心旺盛なJD)明治のお金って、すごく立派だったね〜!“円”が生まれて、世界とつながってる感じがした!



だしょ?でも次の“大正時代”はね、貨幣的には大きな変化は少ないけど…文化と暮らしがぐーんと変わる、ロマンあふれる時代なんだよ!



ロマン?なんだか気になる〜。どんなお金が使われてたの?



明治から引き継いだお金がまだまだ主役!でも、そこには“静かなる進化”があったんだ。さっそくのぞいてみよう!
🌸 大正時代とはどんな時代?


大正時代(1912〜1926年)は、明治から昭和へと橋渡しをする、わずか15年ほどの短い期間でした。
しかしその中で「大正デモクラシー」や「都市化・インフラ整備」「モダン文化の台頭」など、新しい風が吹き込まれる時代でもありました。経済の近代化が定着し、庶民の暮らしにも“お金”がより密接に関わっていくようになります。
貨幣そのもののデザインや制度には大きな変更はなかったものの、“紙幣と銀行”“貯金と給料”“買い物文化”など、お金の“使い方”が次第に変化していったのです。
🏦 引き継がれた貨幣と日常の中のお金




大正時代に使われていた主な貨幣は、明治時代後期の貨幣とほぼ同じです。
- 金貨:10円・20円金貨(※発行数は少なくなる)
- 銀貨:1円銀貨(主に海外向け)
- 銅・ニッケル貨:1銭・5銭・10銭など
- 紙幣:日本銀行券(大正兌換銀行券)
この時代になると、貨幣の使用は都市部を中心にますます“紙幣中心”となり、日々の買い物や給与の支払いも紙幣や硬貨で行われるようになりました。
また、農村部でも“郵便貯金”や“農協”などを通じて貨幣経済が根づきつつあり、お金はますます生活の基盤として浸透していきます。
🛍️ 大正モダンと消費文化


都市の拡大とともに「買い物文化」も花開きます。百貨店、喫茶店、洋装店などが登場し、
- 「おこづかいで買うレコード」
- 「カフェで1杯5銭のコーヒー」
- 「帽子とスカーフのおしゃれ買い」
といったように、貨幣が“夢や楽しみ”に使われるようになっていきました。
このころには「お年玉」や「月給袋」など、お金に名前をつけて管理する文化も芽生えはじめ、家庭内でのお金の位置づけもより明確になります。
📉 金貨の衰退と新素材の登場


大正時代は、貨幣制度が安定した一方で、金貨の流通量が急減します。
理由は第一次世界大戦(1914〜1918年)の影響です。戦争による物資不足と価格高騰により、金貨は“実用貨幣”ではなく、“保管貨幣=貯蔵資産”へと変わっていきます。
この結果、金貨は日常の支払いから姿を消し、代わって紙幣・小額硬貨が本格的に主役となっていきました。
また、ニッケルを素材とする硬貨の登場など、新素材への切り替えも徐々に進んでいきます。
🧠 たまちゃんの豆知識コーナー!



・大正時代の「5銭硬貨」はカフェの定番通貨だった!
・1円は、当時の労働者の“日給”に近い金額だったよ。
・「こづかい帳」が流行り始めたのもこの時代。特に女学生に人気!
📚 銀行と貯蓄の定着
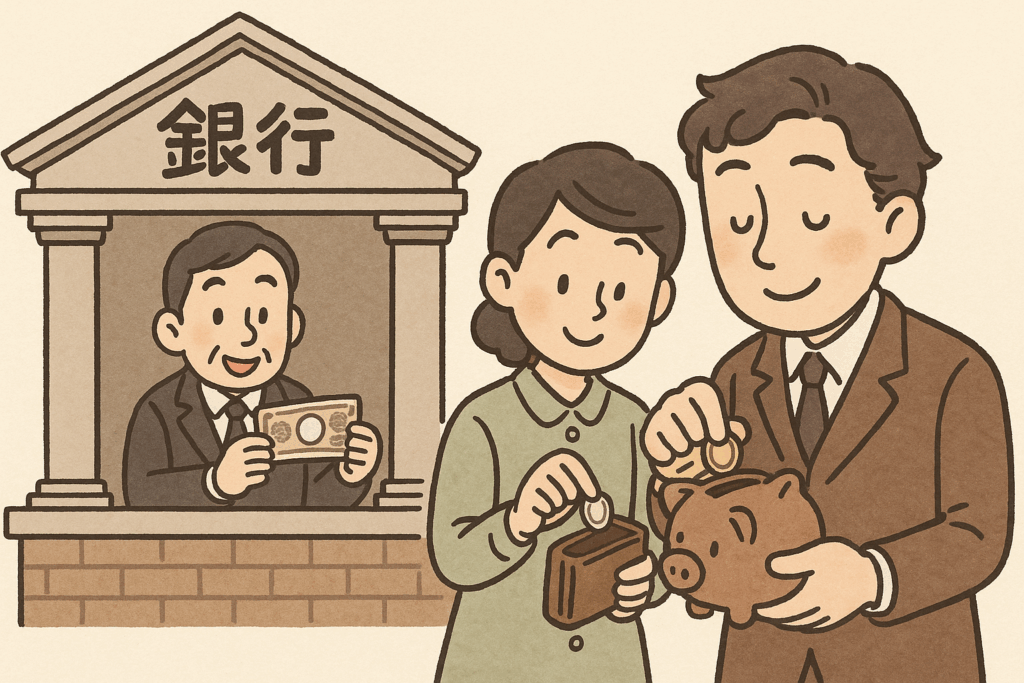
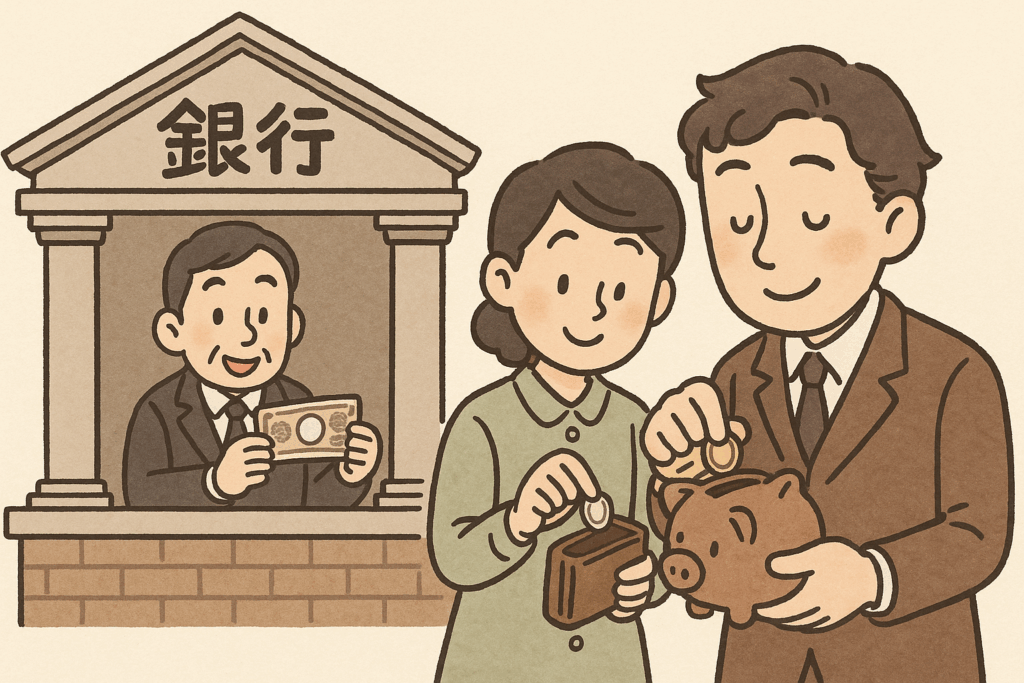
明治時代に生まれた“銀行”は、この大正期により地域に広がっていきました。
- 「月給は銀行振込」
- 「通帳でお金を管理」
- 「定期預金で将来に備える」
というように、都市部では“貯金するのが当たり前”の文化が育っていきます。
一方で、銀行制度が地方にまでは届いていなかったため、郵便貯金や農協、信用金庫といった現在も続く“身近なお金の預け先”も重要な役割を担っていました。
🎭 大正ロマンと貨幣文化の広がり
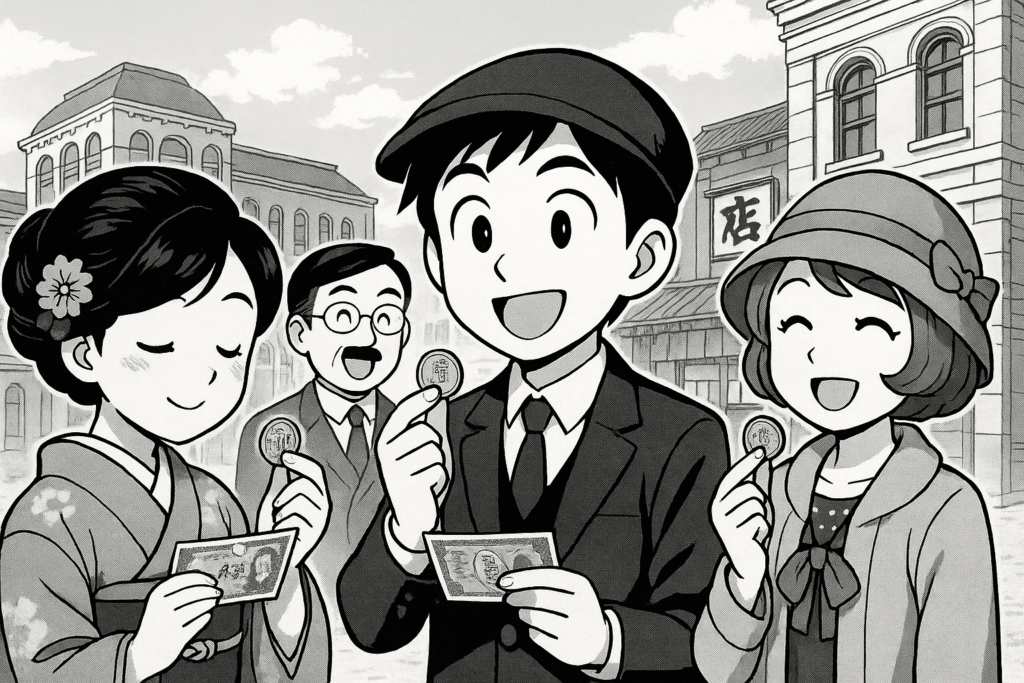
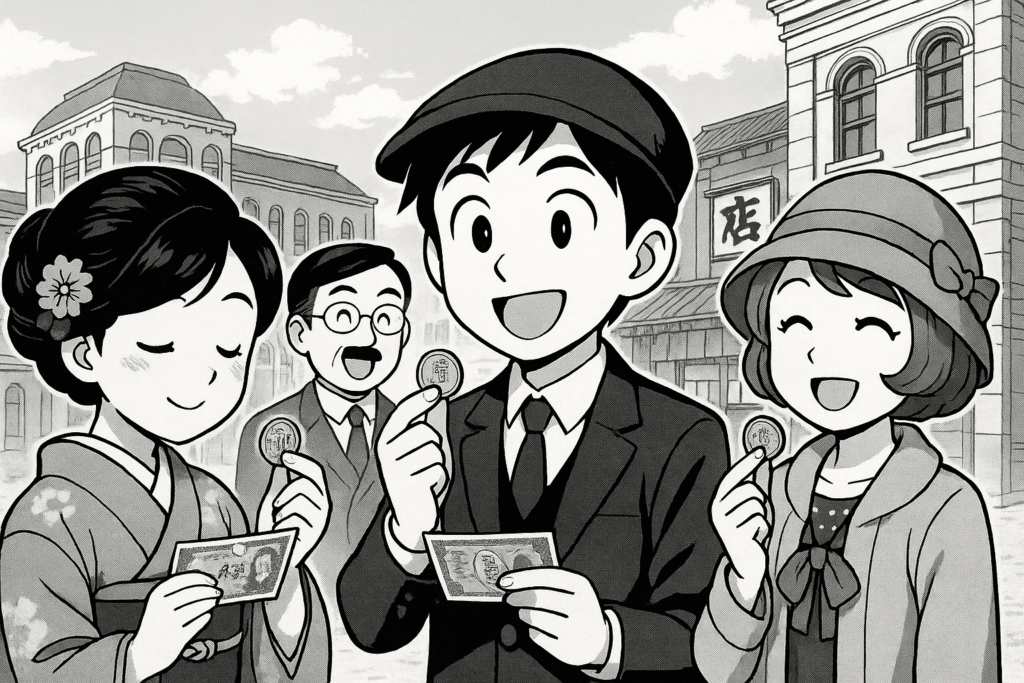
「ハイカラ」「モダンガール」「大正デモクラシー」…
新しい風が吹き込んだこの時代、貨幣もまた“生活のデザインの一部”となっていきます。
- 袋入りの給料を「月謝袋」に入れて渡す文化
- 雑誌付録の「紙幣風おもちゃ」で遊ぶ子どもたち
- カレンダーに給料日と支出を書き込む“家庭会計”の習慣
それまで“難しいもの”とされてきたお金が、“見える・使える・数えられる”存在として日常に定着していったのです。
🌐 海外とのつながりと貨幣
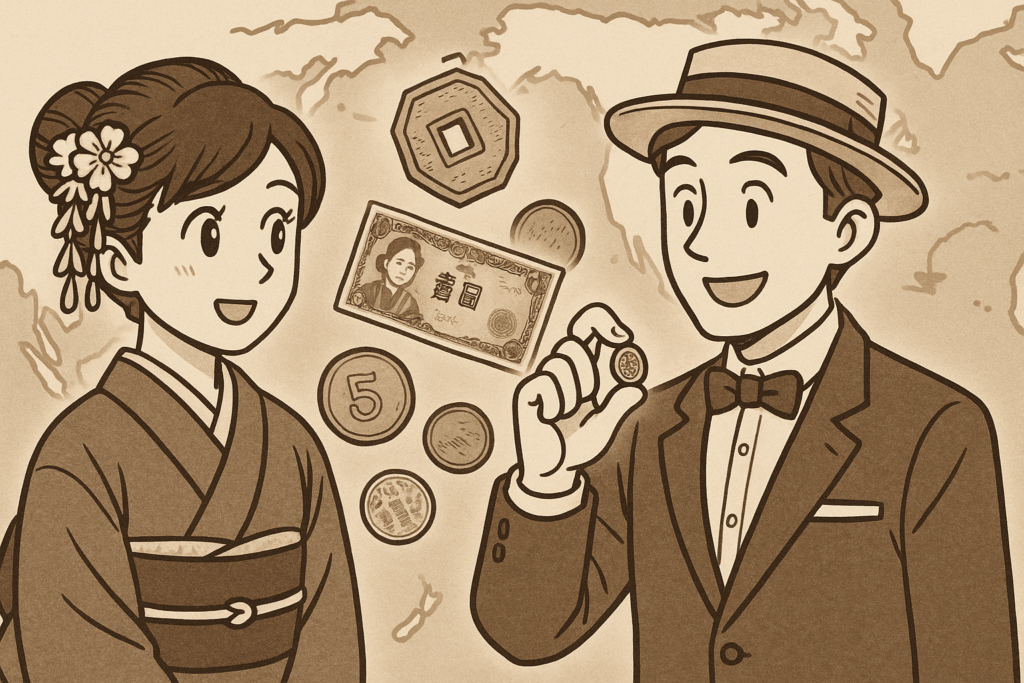
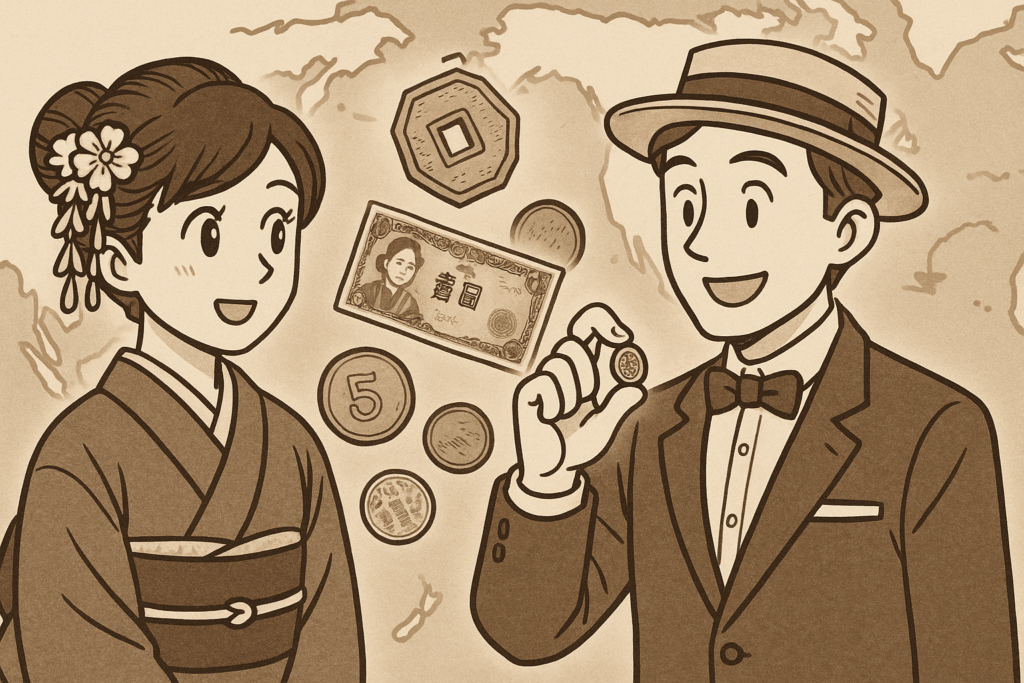
大正時代は、日本が世界の中で“経済的プレイヤー”として位置づけられ始めた時代でもあります。
- 第一次世界大戦による経済成長
- 外貨決済で使用される「1円銀貨」
- 日本製貨幣がアジア諸国へ流通
こうして貨幣は、日本国内だけでなく、国際的な“価値の媒介”として活躍するようになっていきました。
✨ ももの気づきメモ



大正って、なんだか“おしゃれで進化してる”感じがするね!お金の使い方が、生活といっしょに変わっていくのが面白い!



そうそう!大きな制度の変化はなくても、“使い方”が変われば、“お金の価値”も変わってくるってことだね!
🏁 まとめ:移行期の静かな革命


大正時代は、貨幣制度そのものの改革は少なかったものの、「生活と貨幣の関係性」が変わった重要な時代でした。明治から受け継いだ近代貨幣は、都市と地方、家庭とビジネス、消費と貯蓄という様々な場面で定着し、次なる“昭和の激動”へと橋をかけていきます。



次章ではいよいよ戦争と経済が交差する、「昭和戦前」の時代へ――。 貨幣の運命が大きく揺れるその時代を一緒に見に行こう!